
きょうの料理レシピ
桜鯛とクレソンのバターあんかけ
昆布だしベースの煮汁で蒸し煮にし、バターも加えてまったりと仕上げます。骨付きの切り身をそのまま使って、骨のうまみをとり込み、煮汁を片栗粉でとじて余すところなく味わう“始末の精神”の逸品です。

写真: 蛭子 真
エネルギー
/160 kcal
*1人分
塩分/4.5 g
*1人分
調理時間
/25分
*冷蔵庫におく時間は除く。
材料
(2人分)
- ・たい (切り身/骨付き) 2切れ(120g)
- ・ゆでたけのこ (穂先側の上部) 100g
- ・クレソン 25g
- ・そら豆 (さやから出す) 10コ
- 【煮汁】
- ・基本の昆布だし カップ1
- *下ごしらえ・準備参照
- ・削り節 8g
- ・酒 大さじ1
- ・みりん 小さじ2
- ・うす口しょうゆ 小さじ2
- ・塩 小さじ1
- 【水溶き片栗粉】
- ・片栗粉 大さじ1
- ・水 大さじ2
- ・木の芽 適量
- ・塩
- ・バター
下ごしらえ・準備
基本の昆布だしのとり方
1 だしが早く出るように昆布45gを数かけに割る。
2 鍋に水1.2リットルと1を入れて一晩おく。弱火にかけて沸騰しないように30分間温め、昆布を取り出す。
! ポイント
大阪の昆布だしの特徴は、北海道の道南で採れる真昆布を使うこと。上野さんの店では水に浸して一晩おき、翌日に火にかけ、沸騰しないように3時間かけて濃厚な昆布だしをとり、「まったり味」のベースにします。
つくり方
1
【煮汁】をつくる。鍋に基本の昆布だしを入れて沸かし、削り節を加えて火を止める。5分間おき、ざるでこす。残りの調味料を加える。
2
たけのこは食べやすい大きさに切って熱湯に入れ、中火で1~2分間ゆでて取り出す。そら豆は塩適量を入れた熱湯でゆでて冷水にとる。紙タオルで水けを拭き、薄皮をむく。
3
たいは皮側に包丁で切り目を2か所入れ、塩小さじ1/4をふって冷蔵庫に30分間おく。熱湯にサッとくぐらせ、冷水にとってウロコとぬめりを取り、紙タオルで水けを拭く。
! ポイント
熱湯にくぐらせると、皮に残った汚れやくさみが取れやすくなる。
4
フライパンに1を入れて中火にかけ、煮立ったら3のたいと2のたけのこを加える。ふたをして5分間蒸し煮にする。
5
ふたを外してクレソンと2のそら豆を加え、サッと火を通す。火を止め、【煮汁】をきって器に盛る。
! ポイント
クレソンはすぐ火が通るので煮すぎないようにする。
6
フライパンに残った【煮汁】にバター4gを加えて中火にかけ、【水溶き片栗粉】を混ぜ合わせて様子を見ながら少しずつ加える。とろみがついたら火を止め、5にかけて木の芽をのせる。
! ポイント
【煮汁】にバターを加えることで香りとコクをプラスする。
全体備考
●「基本の昆布だし」の保存
冷蔵庫で3日間
◆大阪料理の特徴◆
・特徴1:食い味=まったり味
江戸時代、流通の中心を担った大阪は昆布の集積地であったため、昆布だしが発達しました。昆布だしでつくる、まろやかで深みのある「まったり味」は「なにわの食い味」と呼ばれます。
・特徴2:始末の精神
商業が盛んな大阪では、食材をむだにせず使いきる「始末の精神」が根づいています。この精神は、例えば大根の皮は堅いので、堅さを生かした食べ方を考える「合理性」につながります。
きょうの料理レシピ
2025/04/23
満喫!なにわの"食い味”
このレシピをつくった人

上野 修さん
高校卒業後、三重県志摩市のホテルでフランス料理の修業を重ねる。そののち大阪に戻り、1994年に修三さんの店を継ぎ、2代目となる。フランス料理のエッセンスを随所に取り入れながらも、浪速料理の味とスタイルを守り続けている。
他にお探しのレシピはありませんか?
おすすめ企画 PR
今週の人気レシピランキング
NHK「きょうの料理」
放送&テキストのご紹介
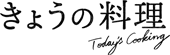

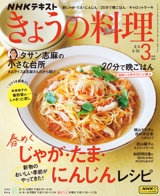
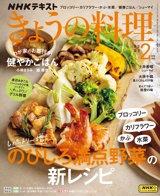



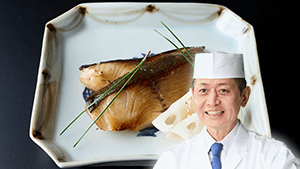









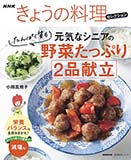
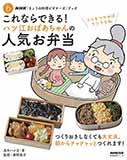

つくったコメント